3月25日夜、宮中晩餐会が皇居・宮殿で開催されました。
約6年ぶりの宮中晩餐会であり、また愛子さまの晩餐会デビューともなったことが注目されました。
ところが、ドレスコードが平服に変更されたことに対し疑問が生じています。
愛子さまの記念すべき晩餐会デビューが平服となった理由について、調査しました。
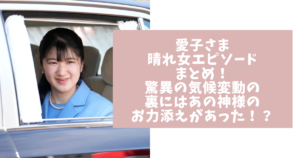
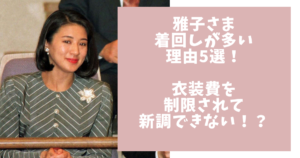
愛子さま宮中晩餐会デビューは平服
3月25日に行われた宮中晩餐会は、成年皇族として愛子さまが初めてご参加される晩餐会となりました。
国賓としてブラジルのルラ・ダシルバ大統領夫妻を迎え、日本とブラジルの外交関係樹立130年の節目を祝われました。

今回の宮中晩餐会で注目されたのは「カジュアルでリラックスした雰囲気」。
天皇皇后両陛下は、これまで取り分けるスタイルだった料理の提供が、銘々皿に乗って出てくるという形に変更。
配膳の回数を減らし、より参加者がリラックスした雰囲気を保ちたい
という、天皇皇后両陛下のお気持ちに沿った変更点だったそうです。
天皇皇后両陛下がよりリラックスモードの晩餐会を望まれる中、国賓として招かれたブラジルのルラ・ダシルバ大統領夫妻にもご要望が。
それは、カジュアルな雰囲気を楽しみたいというお気持ちから、ドレスコードを平服にしてほしいと希望があったことだそうです。

宮中晩餐会において、両国の出席者が平服というケースは初めてのことだそうで、このドレスコードにも注目が集まりました。
もっとも多かった意見は、
と、残念がる声だったようです。
過去の晩餐会はどうだった?
前回の宮中晩餐会は、2019年にアメリカ・トランプ大統領夫妻を招いて行われた回。
当時のドレスコードは男性がタキシード、女性がロングドレスで盛装していました。

愛子さまは未成年だったためにいらっしゃらなかったものの、天皇皇后両陛下、そしてトランプ大統領夫妻の華やかな装いが素敵でしたね。

しかし、2019年の晩餐会でもティアラは着用されていないようです。
実は、宮中晩餐会の国賓が王族でない場合には、皇族は勲章とティアラを着用されないことになっているのだそう。
2019年の宮中晩餐会に招かれたのはトランプ大統領夫妻でしたので、ティアラはなしだったのですね。

ちなみに、2014年にオランダ国王夫妻を迎えた宮中晩餐会では、雅子さまが当時の皇太子妃「第二ティアラ」を身に着けられていました。

やはりティアラがあるといっそう華やかですね!
2016年にベルギーのフィリップ国王夫妻を招いた宮中晩餐会でも、同じティアラをお召しになっていました。

皇族女性のティアラ姿はめったにお目にかかれるものではありませんから、思わず見とれてしまいます。
その前の宮中晩餐会ではブータンのワンチュク国王夫妻を招待していますが、このときは事前のドレスコード調整があり、ティアラはなかったそうです。

このように、同じ宮中晩餐会であっても社会情勢などをふまえて、ドレスコードが調整されることは珍しくないのですね。
ドレスコードはどうやって決まる?
宮中晩餐会のドレスコードは、過去の回を振り返るとさまざまだったことが分かります。
招待国の国賓が民族衣装で参加しても、皇族側がタキシードと和装(=準礼装)のみのこともあったそう。
招待するのが王族でなければティアラは着用する必要がない、という規定はあるものの、相手が王族=ティアラ必須というわけでもないようです。
招待する国賓が誰なのかよりも、男性皇族の衣装を先に決め、それに見合った女性のドレスコードが決まっていくそう。
たとえば、男性皇族が燕尾服を着用することになれば、それに対応する女性皇族の正礼装はローブデコルテとティアラです。

ティアラの有無が先に決まるのではなく、ドレスコードによってティアラをつけるかどうかが決められるのですね。
また、ドレスコードはどちらかの国から指定があるわけではなく、相手の国とよく相談した上で決定されるそうですよ。
平服になった本当の理由
今回の宮中晩餐会では、ドレスコードが「平服」となりました。
これまでの宮中晩餐会を振り返ってみても、準礼装になるケースはよくありましたが、平服は初めてのことだったそうです。
ドレスコードの調整があるとはいえ、国賓を招いての晩餐会で「平服」というのは、国民の私たちも驚きましたよね。

しかも、ブラジル大統領夫妻の要望だったなんて…
なぜ、6年ぶりに行われた宮中晩餐会が「平服」となったのでしょうか?
全国的に報じられたニュースでは「ブラジル側がカジュアルな晩餐会を望んだから」とありますが、そうではない理由も隠されていそうです。
愛子さまが皇位継承者ではないから?


宮中晩餐会のドレスコードが「平服」になるというのは、望ましいことではないと考える国民が多くいます。
もちろん、親睦をさらに深めるためにリラックスした雰囲気を大切にしたいという思いは素敵です。
しかし、ドレスコードというのは参加者たちの品格や、立ち振る舞いすべてに関わるもの。
相手に敬意を払った衣装を身にまとうことで、開催国と相手国がお互いにリスペクトを示すこともできますよね。
せっかくそのような場でお会いできる機会なのに、ブラジル側が平服を望んだのは
愛子さまが皇位継承者ではないから?
と囁かれています。
愛子さまは現在の法律では、天皇になることはできません。
愛子さまは天皇家の長女ですが、次期天皇は実弟の秋篠宮殿下であり、その次は秋篠宮殿下の長男・悠仁さまです。


世界中が注目している、日本の皇位継承問題。
国内では「愛子天皇」を熱望する声が溢れかえっているものの、現行の制度を変更するのは簡単なことではないでしょう。
愛子さまが天皇になる可能性が現時点でゼロである以上、相手国からのリスペクトが感じられなかったという声がありました。
皇室側がブラジルのせいにしているから?


宮中晩餐会のドレスコードが平服になったのは、ブラジル大統領夫妻の要望だったといわれています。
しかし、中には



招待されている立場で「平服」を指定してくるなんて、そんな失礼なことするかな?
という声が聞かれるのも事実です。
確かに、6年ぶりの宮中晩餐会に招待された立場で「平服が良い」と希望するのは、少々図々しい気も…。
そのため、表向きは「ブラジル側の要望で」とされていながらも、実際には違うのではないかと推測されています。
ブラジル側の気持ちを汲み取ろうとした皇族側が先走り「きっとカジュアルに平服が良いだろう」とし、相談に持ち込んだ可能性もあるそうです。
もしそれが事実だとしても、天皇皇后両陛下に悪気があったわけではないでしょう。
招待客にリラックスして楽しんでいただくために、先読みして気を遣われたのかもしれません。
ブラジルのルラ・ダシルバ大統領は生まれながらの苦労人で、貧困地域で生まれ、幼い頃からさまざまな仕事を経験してきました。


飢餓をなくし、格差を縮小することに主眼を置く情熱を持ったルラ大統領に、天皇皇后両陛下が敬意を示しているのは言うまでもないでしょう。
そんなルラ大統領夫妻に、心から気を許し楽しんでほしいという思いの表れだったのかもしれませんね。
しかし国民の間では、
本当は皇室側が平服にしたのに、ブラジルの要望だということにしている可能性
が囁かれているようです。
と、宮内庁を疑う声もありました。
日本経済が貧しすぎるから?
皇室側が平服を要望し、それをブラジルのせいにしているという推測があるとお話しました。
この推測にはさらに裏があり、日本経済が貧しすぎるがゆえに平服にせざるを得なかったのではないかというものです。
日本は豊かな国であるものの経済は停滞しており、愛子さまのティアラもおば・黒田清子さんに借りたもの。


天皇家の長女にティアラも作れないような国だとブラジルが判断した場合、
豪勢な晩餐会にはしないほうが良いかもしれない…
と気を遣わせてしまった可能性もありますね。
愛子さまのレベルに合わせたから?
華やかな宮中晩餐会のドレスコードが平服になったのは、初めてのご参加となる愛子さまに合わせたからではないかといわれています。


愛子さまの晩餐会デビューとなった今回ですが、ドレスコードのほかに配膳方法も「カジュアル化」されました。
これらは、初めてのご参加となる愛子さまが居心地よくなるよう、調整されたものではないかといわれています。
さすがにここまでの推測が正確かどうかはわかりませんが、SNSでは
と、レベルを下げられたことに批判的な意見を寄せる人の声が目立っています。
愛子さま平服でもキラキラしてる!
宮中晩餐会のドレスコードは平服になりましたが、愛子さまは平服でも持ち前の華やかなオーラを放っていました。


正装であれば和装やローブ・デコルテなど、普段あまり見られない愛子さまのお姿が見られたのでしょうか。


愛子さまは2024年の「新年祝賀の儀」で、おばである黒田清子さんから借りたティアラをお召しになっていましたよね。


愛子さまの凛とした控えめなオーラにティアラがマッチしていて、とても神々しかったのを覚えています。
今後、王族を招く晩餐会が行われることになれば、次こそ愛子さまのティアラ姿を拝見できるかもしれません。
ますますお綺麗になっていくであろう愛子さまのお召し物にも、注目が集まるでしょう。
まとめ
3月25日に行われた宮中晩餐会での、ドレスコードについてまとめてみました。
約6年ぶりという記念すべき宮中晩餐会は大成功に終わりましたが、私たちが気になった点の1つはドレスコード。
愛子さまの晩餐会デビューとなった今回、平服での開催には賛否両論ありました。
平服であっても、愛子さまは持ち前の華やかで柔和なオーラを放っていましたね。
ますます美しくご成長される愛子さまの、和装や正装姿も見られることを期待しましょう!
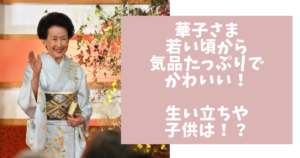
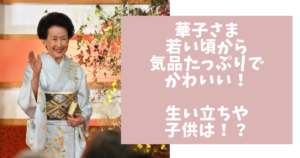

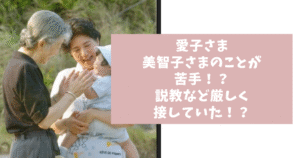
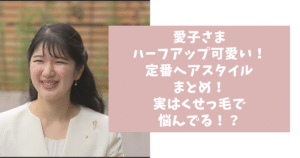


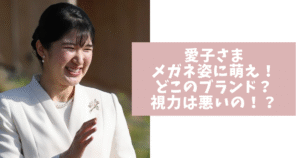
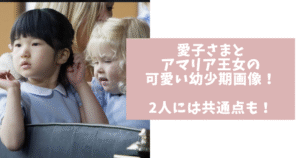
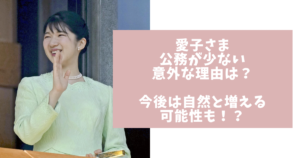
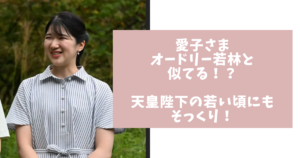
コメント